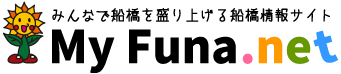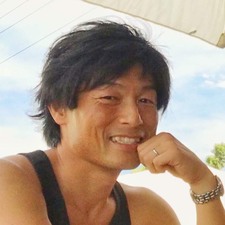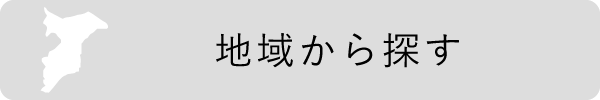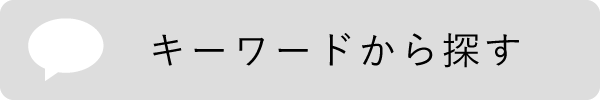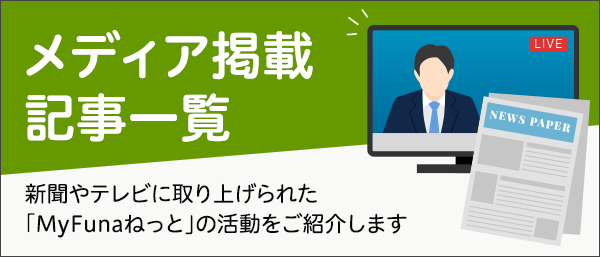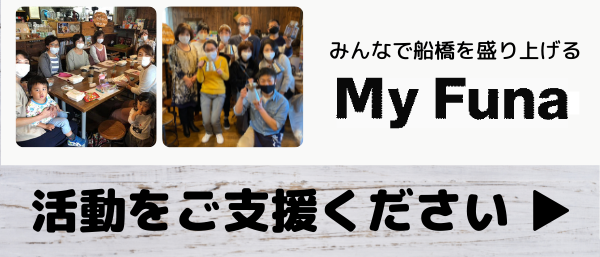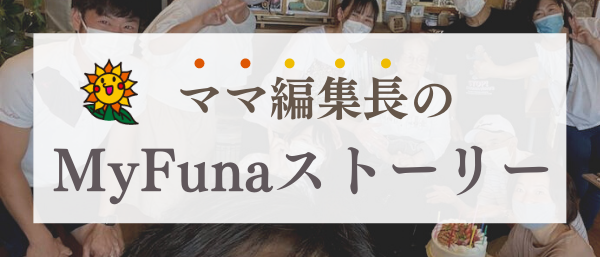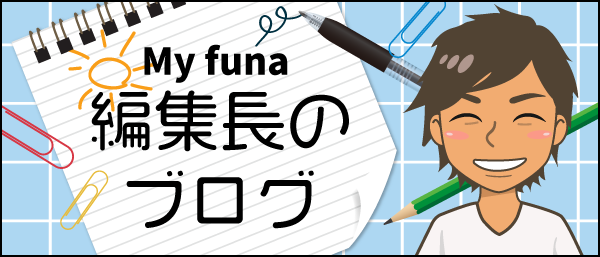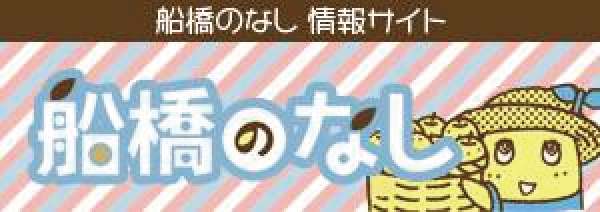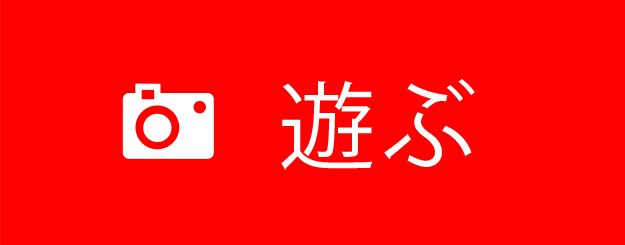7/25(木)習志野市津田沼の八坂神社で100年目の祭礼
コロナ禍を経て道路を封鎖した盛大な祭礼開催
津田沼駅北口から徒歩5分ほど、商業施設に囲まれた津田沼一丁目公園(習志野市津田沼1-4-34)で100年目を迎える八坂神社の祭礼が7月25日、船橋市前原地区と習志野市津田沼一丁目地区の商店主や住民ら氏子衆によって行われた。
同神社は明治40(1907)年に津田沼駅北口の前原地区笠間稲荷神社を祭ったのが始まりとされている。大正13(1924)年、京都の八坂神社の分社として「スサノオノミコト」を祭ったことから八坂神社を建立した。
神事は例年7月14日に開催してきたが、神輿の渡御(とぎょ)は曜日と津田沼周辺のイベント開催日程を考慮して実施してきた。
この日、津田沼一丁目公園で行われたアイドルや地元で活動するアーティスによるステージ、キッチンカーなどの出店によるイベントと合同開催となり公園ではにぎやかな催しが行われた。
これと対比するように八坂神社では厳かな雰囲気に包まれた神事が行われたのち、神輿の宮出し、威勢の良い掛け声とともに氏子や地元商店主らに担がれ神輿が道路を片側封鎖した例年通りのコースで神輿渡御を行った。
八坂神社建立当時は、現在Viit(船橋市前原西2-19-1)がある場所で広大な敷地を誇っていたという。境内には舞台もかけられ、毎年7月13日~15日に渡り祭礼を行い多くの人が訪れたという。
津田沼駅北口の土地区画整理事業で昭和50(1975)年に現在の位置に移転。昭和56(1981)年には千葉県より「宗教法人八坂神社」の認定も受け二宮神社の宮司が神官を兼務するようになった経緯がある。
祭礼は氏子を代表する4人から順番に総総代を出し、祭礼実行委員長を務める形で代々受け継がれてきたという。
※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください
 Sponsored by MyFunaサポーター
Sponsored by MyFunaサポーター