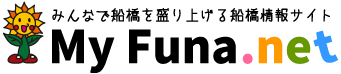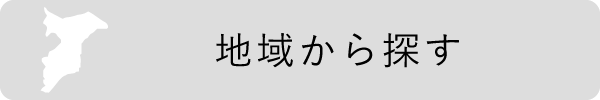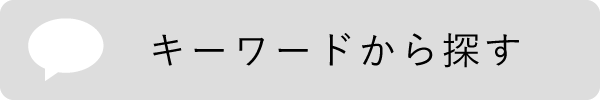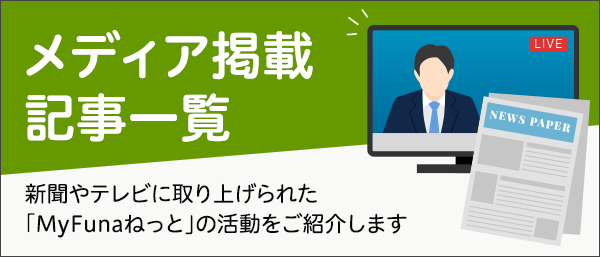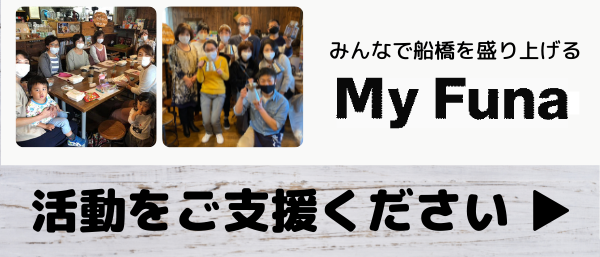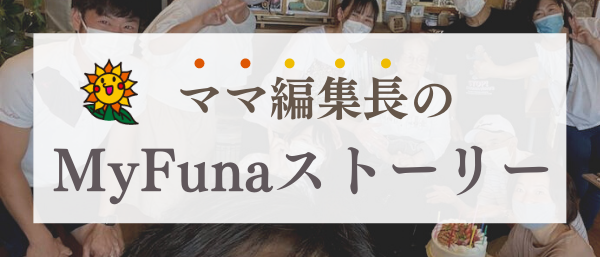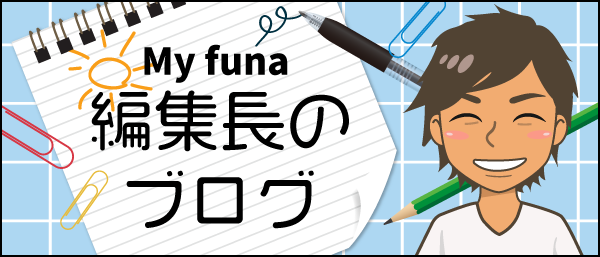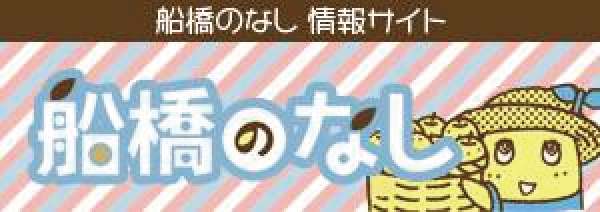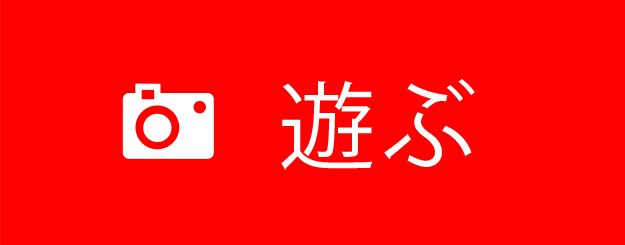コラム
地域でお金を回すこと vol.39
まいふな編集部には正社員と呼ばれる雇用体系のスタッフは一人もいません。16年前に編集部を立ち上げた際は正社員3人、外注スタッフ3人、入力や電話番など補助業務としてパートさん数人という体制でスタートしました。
当初は「正社員で採用し、給料を支払いながら仕事を教えていく」という常識的な組織体系で事業運営をしてきました。しかし16年の中で「正社員」と「外注スタッフ」が持つ意識の差について考えることが多くなり、結果として今の形に落ち着きました。
人が仕事をする時に「自分がやりたいと考えていることを選んで就職している」と思っていたのですが、多くの人は「生きるために仕方なく就職している」のであって、「その中で何となく興味の持てそうな仕事をしている会社を選んでいる」場合が多いこと。しかしその中で「たまたまやりがいを感じて天職だと認識する」場合もあり、そうでない場合は「こんなはずじゃなかった」と、感情を押し殺し給料に対する義務感で奴隷のように働いているという人も少なくないと気が付きました。
もちろん、我慢して仕事を続けることで自分の天職を見つけられることもありますし、継続することの大切さも理解しているつもりです。
私も、会社員時代に本当に営業職が嫌で鬱になり、自殺を考えるようになった経験があります。しかし、自分らしい営業のやり方を見つけて成果を出せるようになり「石の上にも3年だなぁ」という成功体験を積みました。こうした過去の成功をもとに昔の大人は「我慢することの美徳」を若い人に課してきたのかもしれません。
しかし近年、事業の寿命は昔よりも短くなってきました。昭和から平成を経て令和に至る中で組織は変革し続けなければ生き残れない、考え続けなければ価値を示し続けることができない時代になってきたと言えます。
そうした時代に対応するために働き方が多様化し、政府主導で「副業」や「複業」が解禁されてきたのかもしれません。考え方や働き方が多様化してくると外の考え方や文化を組織の中に入れる必要が生じます。それまで均一の価値観で組織づくりをしてきた企業や団体にとっては少なくないストレスを抱えることでしょう。外の組織で経験を積んできた人の考え方、若い人の価値観、男女の考え方や特徴差をふまえ、俯瞰した概念を採り入れることが組織変革や新しい発想、新しい社会への対応につながってくるのかもしれません。
私たちまいふな編集部は日々そのようなことを考え、多様な働き方ができる組織作りを続け、皆さんのお手元にまいふな本誌やインターネットニュース、SNSを活用した情報発信などを手掛けてきました。雇用も業務委託も突き詰めると契約書一枚の関係性。日本人は欧米諸国のようにルールで縛るよりも、人と人とのつながりの大切さ、人の意識が向かっている方向に主眼を置いて組織やチーム編成をする方が向いてるのかもしれないとボランティアを通じて実感します。
株式会社myふなばし・株式会社フィット 代表取締役
船橋経済新聞&外房経済新聞 編集長
市場カフェ マスター
一般社団法人船橋市観光協会
包括地域プロデューサー
山﨑健太朗

Twitter(@ MyFunabashi)
ほかにも、さまざまな情報発信をしています!
★YouTube「やまけんちゃんねる」山﨑が船橋市内中心に活躍している経営者をゲストに呼んでインタビューしています
★note「やまけん」
★ブログ「主婦と高齢者で地方活性化を実現する編集者・ライターという働き方」
※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください