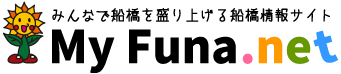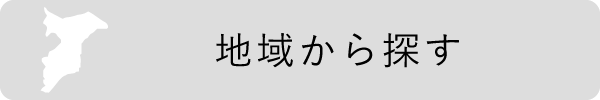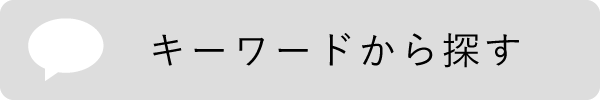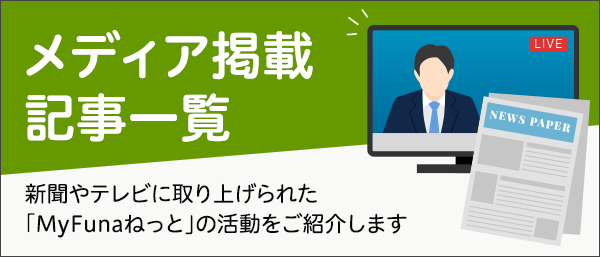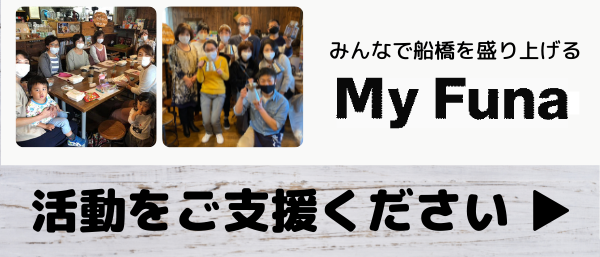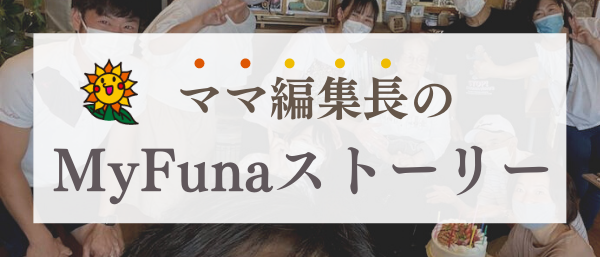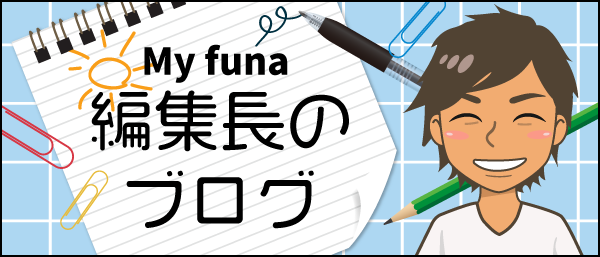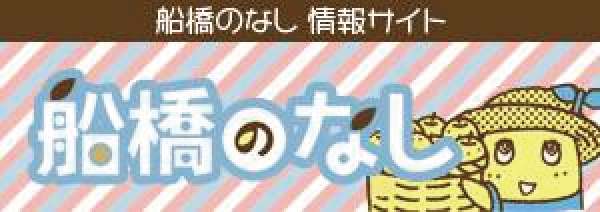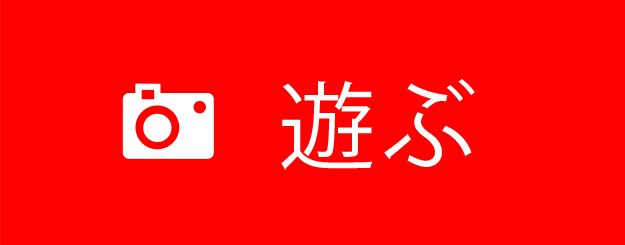コラム
新型コロナの先にあるもの vol.28
船橋市内にも増えてきた「コワーキングスペース」。「集中して仕事を進めるための目的で利用するもの」と「人が常駐、誰かに会うため利用するコミュニティ的要素が強いもの」という二通りのパターンに分けられるように思われます(あくまで私見ですが)。
前者の例でいえば、JRなどの駅内にある個室ブース「ステーションワーク」や最近テレビCMでもお馴染みになりつつある「ZXY(ジザイ)」など。各主要駅に展開しており、決済や利用予約はオンライン。細切れの時間を集中作業に充てたり、リフレッシュのために利用したりと有効活用されているようです。
後者の例は、コミュニティマネージャーと呼ばれる「利用者一人ひとりのことを把握しているスタッフ」が常駐する場合が多く、利用者はコミュニティマネージャーに会いに、または他の利用者とのつながることを楽しみにコワーキングスペースを利用します。
コミュニティマネージャーには専門的な技術が求められます。「この人とこの人の仕事は相性がいいぞ」「この人はこの仕事が得意だけど、この仕事は苦手だぞ。この人と組ませたら機能するかも」とか、「この人とこの人は性格的に合わなそうだから、この人を間において付き合ってもらった方が良さそうだぞ」など細かい部分まで気を使って人と人との間を取り持ちます。
こうして、コミュニティマネージャーがつなげた人材同士が新しい価値を生み出し、新しい仕事を創り出します。「人と人とのつながりが生み出す価値」は地域にとって大きな影響を与えます。
地方のコワーキングスペース立ち上がったチームはその街の課題解決を目的としたチームであることが多いです。彼らが手掛けるプロジェクトは街の課題をどんどん解決していきます。
一方で、都会的なコワーキングスペースの場合、もっと大きな社会課題がターゲットであったり、企業からオファーのあった案件を完成させるためのチームである場合が多いように感じられます。
では、船橋や津田沼に増えているコワーキングスペースはどうでしょう? 現在私たちの地元に増えているコワーキングスペースは、集中作業型や都会型に近いものが多く、地域課題を解決するための新しいチームを生み出す機能は、むしろカフェで多く見られます。地域内の課題をテーマに話し合いの場を設け、それに興味のある関係者らが集まり課題解決のためにチームを構築する…結果的に、地域内で起きている「草の根の課題」がどんどん解決していくのを目の前でいくつも見てきました。それぞれが専門性を持って繋がり合った時に新しい価値が生まれる。「専門性」は唯一無二の物である必要はなく、「チーム内の誰よりもそれに興味がある」という程度で良かったりします。
大切なのは、課題を見つける、自分の得意分野、興味のある分野をチームの力として活かせるかどうかのようです。
株式会社myふなばし代表取締役
一般社団法人船橋市観光協会
包括地域プロデューサー
山﨑健太朗

Twitter(@ MyFunabashi)
ほかにもさまざまな情報発信をしています!
★YouTube「やまけんちゃんねる」山﨑が船橋市内中心に活躍している経営者をゲストに呼んでインタビューしています
★note「やまけん」
★ブログ「主婦と高齢者で地方活性化を実現する編集者・ライターという働き方」
※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください