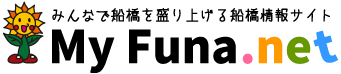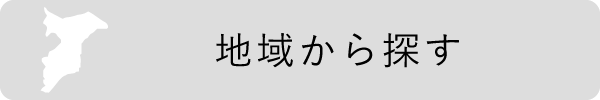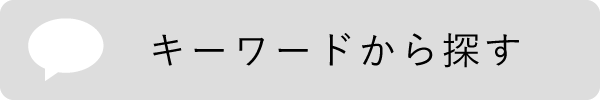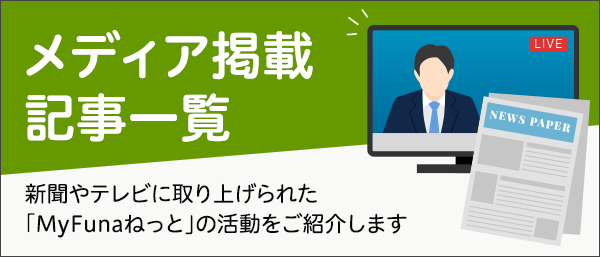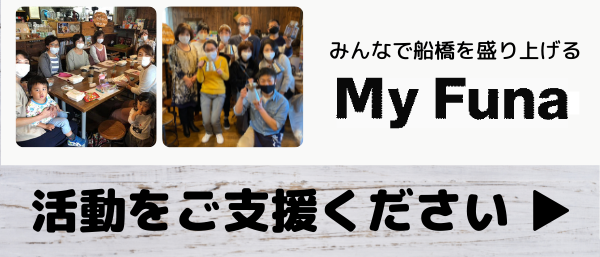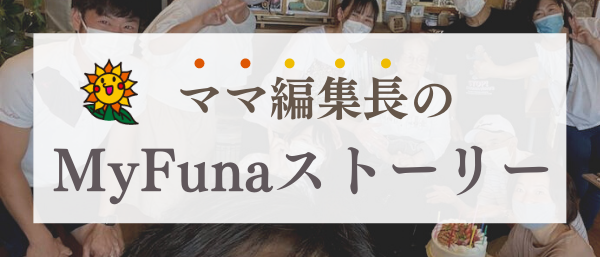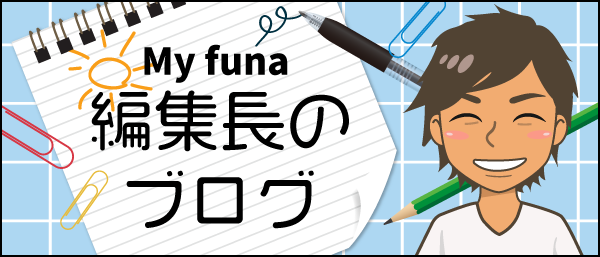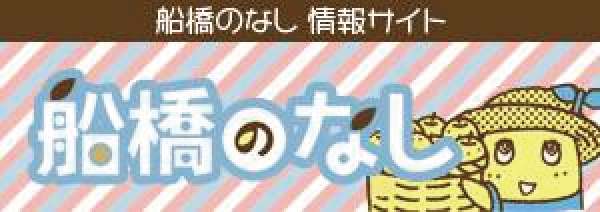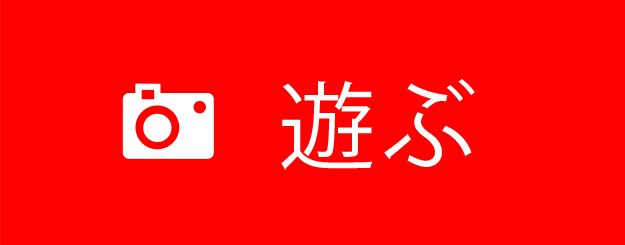コラム
新型コロナの先にあるもの vol.22
私たちが生活する地域社会にはたくさんの「もったいない」があります。
たとえば、返礼品などでもらったお皿やバスタオル、買ったままタンスの肥やしになっている服や月に数回しか使わない自家用車。運営者がいなくて稼働していない自治会館、相続したのを知らないままに放置されている空き家…。ビジネスでも、専門領域をうまく伝えきれずに機会損失しているフリーランス、優秀な従業員が効率よく稼働していない企業、都内で活躍している優秀な人材が地域に住んでいても地域と関わりがないことも…。地域の中で無駄になっているこうした資源を「見える化」することで「もったいない」を活用するのが「シェアリングエコノミー」と呼ばれる、古くて新しい価値です。江戸時代に当たり前だった「リサイクル」を今風にアレンジした感じですかね。
戦後から高度経済成長期にかけて「GDP(国内総生産)」や「GNP(国民総生産)」を世界トップクラスまで押し上げる目的で、国をあげて大量生産・大量消費経済を進めてきました。少しでも安く商品を作ってどんどん売る。新しいものに買い替えて古いものは捨てていく…、消費型の市場経済は「占有」の文化を生み出したともいわれています。三世代同居が当たり前だった日本社会は、戦後復興を目指し、憧れの「団地」を夢見て、テレビ、洗濯機、冷蔵庫の三種の神器を手に入れようとがむしゃらに働きました。高度経済成長期を迎えると憧れの「マイホーム」を手に入れ、カラーテレビ、クーラー、自動車という新・三種の神器(3C)を目指して働いてきました。そしてこの流れは別荘、電子レンジ、セントラルヒーティング…という新しい三種の神器へ移行していきます。そうして手に入れた4LDKの「マイホーム」が立ち並ぶ「閑静な住宅地」は子ども達の独立とともに高齢世帯が残り、高齢化地域と呼ばれるようになりました。「別荘」ともなると、もっと手入れが大変なので、言うに及ばずでしょう…。
一方で、働き盛りの20~30代は新築マイホームの35年ローンに苦しんでいます。これまでの消費・占有型経済と高度経済成長期のような働き方はコロナショックを機に大きく変わったと言えます。コロナ前、政府が主導していたゼロ残業、テレワークなどの「働き方改革」はコロナを機に一気に進みました。クラウドの活用、IOT、キャッシュレスなどをはじめとしたIT化やAI導入、ビッグデータやドローン技術活用による渋滞回避などが現実に迫っている今、地域内にある余剰をどのように活かし、若い世代が地域で気持ちよく生活できる仕組みやコミュニティを作るかは、ヤフーなどの大企業がテレワーク基準の会社経営に舵取りを決めた現代において、地域が避けて通れない話題だと感じています。
株式会社myふなばし代表取締役
一般社団法人船橋市観光協会
包括地域プロデューサー
山﨑健太朗

Twitter(@ MyFunabashi)
ほかにもさまざまな情報発信をしています!
★YouTube「やまけんちゃんねる」山﨑が船橋市内中心に活躍している経営者をゲストに呼んでインタビューしています
★note「やまけん」
★ブログ「主婦と高齢者で地方活性化を実現する編集者・ライターという働き方」
※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください