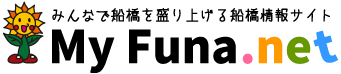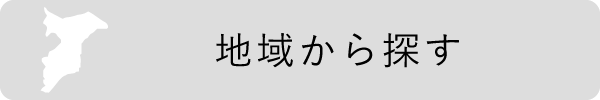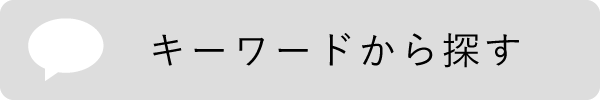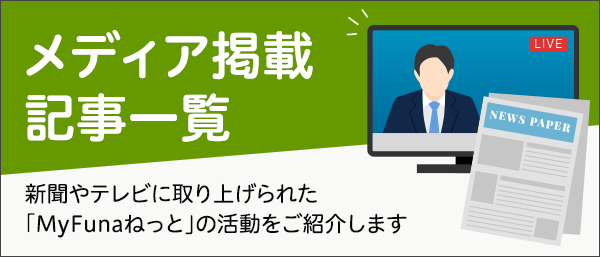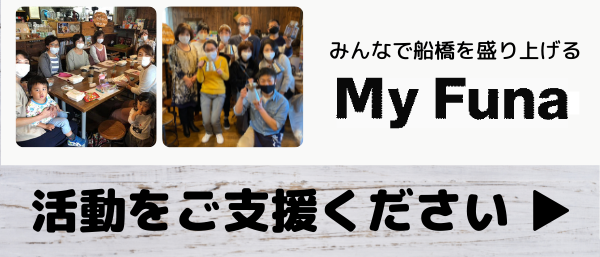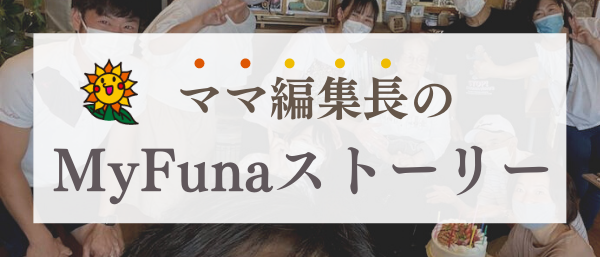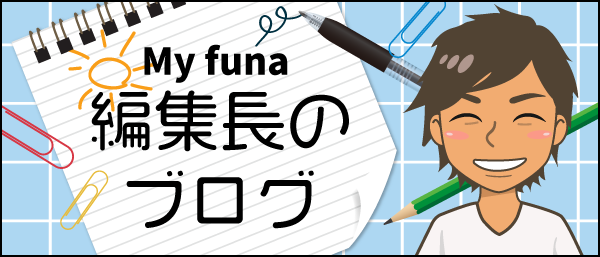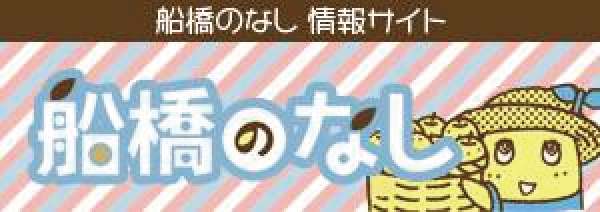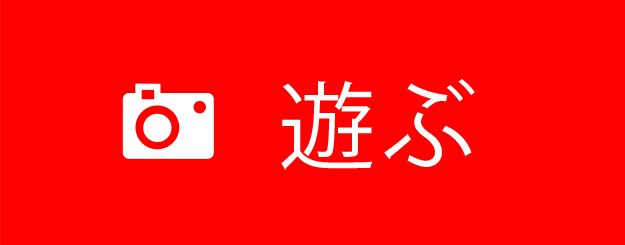コラム
新型コロナの先にあるもの
私たちの給料がどのくらい地域に流れているのかを考えずには地域経済を語れません。仮に30万円の給料をもらっている会社員の場合、税金や社会保険、住宅ローン(家賃)や水道光熱費、自動車に関するローンや維持費(保険含め)、通信費…など、給料をもらった時に既に支払いが決まっている支出を除くと実に5%くらい(※図1参照)しか可処分所得が残りません。この中から、食費や子どもの塾、趣味や外食に使う交遊費などを捻出します。この、可処分所得以外は…その支出の多くが、都心部や海外に出ていってしまうグローバル経済につながっているものです。
住宅や車を購入する時、地元の企業を通じて購入&メンテナンスするなどでこれらの支出の何割かは地域に流れます。食事をする時に、大手のチェーン店ではなく数回で良いので地域の個人店で行う事で地域の中にお金が流れるようになります。インターネット経由でニュースを読むのでなく、新聞販売店で新聞を購読する。通信販売ではなく地域の書店で予約して購入する…そうした少しずつの「不便さ」を敢えて選ぶことが地域経済の活性化につながります。
▼図1

まいふな編集部では、図のような消費内訳を会社員のモデルパターンとして捉え、「少し生活費が足りない」という家庭を対象に、金融教育の提供と副業の促進、福利厚生としての地域通貨振出しを事業として行っていくことで地域内にお金を流す仕組み作りを行っていこうと準備してきました。
金融教育によって、所得が増えたとしても①先に払う支出(ローンなど)ではなく可処分所得へ振り分けていく流れを作り、副業支援で②毎月3~5万円程度の副収入を得られる仕組みを。企業と連携し、地域内でしか使えない制限されたお金(=地域通貨)の発行で③消費をなるべく地域の個人店で消費する仕組み作りをしていきます。地域の消費が活性化することでそこに暮らす住民の生活にどんなメリットがあるのでしょうか?地域で働く人たちの多くがその地域に暮らしています。事業者や働き手の収入が安定する事で地方行政の税収が増え、医療や教育、福祉など地方行政の担う業務が手厚くなります。また、学校や地域内でのボランティアにあたる人材が増え、地域内での事業や治安の向上という効果があると考えています。
株式会社myふなばし代表取締役
一般社団法人船橋市観光協会
包括地域プロデューサー

Twitter(@ MyFunabashi)
ほかにもさまざまな情報発信をしています!
★YouTube「やまけんちゃんねる」山﨑が船橋市内中心に活躍している経営者をゲストに呼んでインタビューしています
★note「やまけん」
★ブログ「主婦と高齢者で地方活性化を実現する編集者・ライターという働き方」
※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください