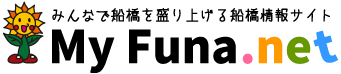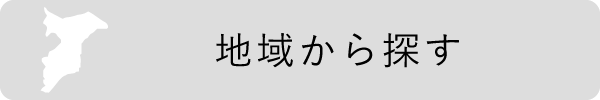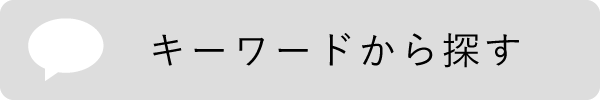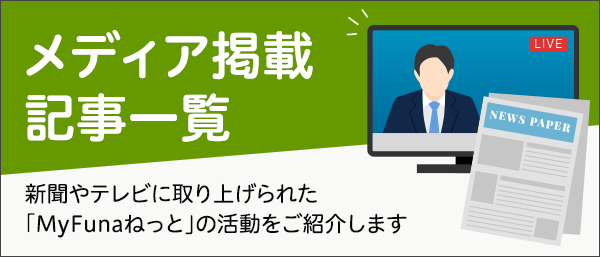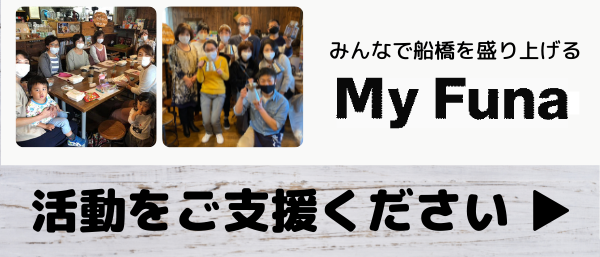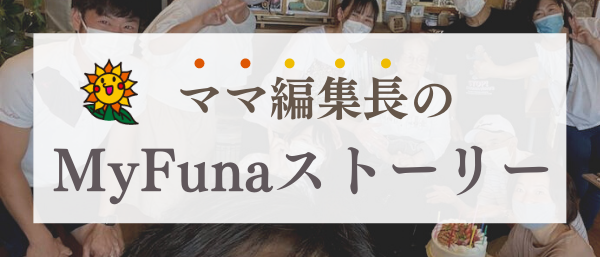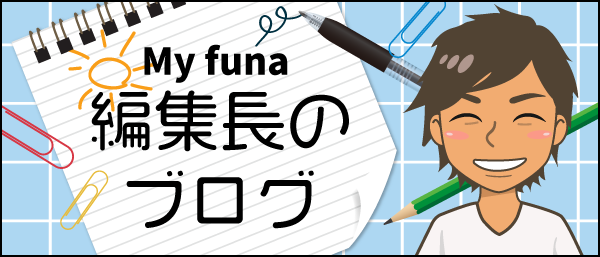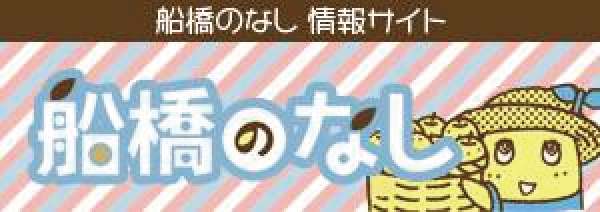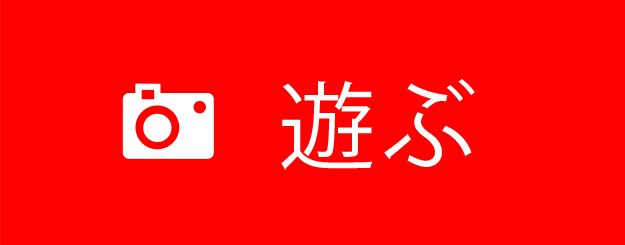コラム
新型コロナの先にあるもの
政府の推奨する新型コロナウイルス感染症の対応策が徐々に明らかになってきました。接客や飲み会の新しいルールが確立され…学校では先生が飛沫感染防止のためにフェイスシールドを逆にして装着するという新ルールも。部活動にも新しいルールが設定されてきました。たった数ヶ月の間にそうした新しい生活様式に合わせたヒット商品やサービスが続々誕生しています。
おそらく…行かなくても良い飲み会は減り、全員が時間と場所を決めてリアルに顔を合わる会議は少なくなり、自宅でも外出先でもオンラインで情報共有できる社会が当たり前になるのでしょう。
これまで海外にわざわざ出張に行っていたビジネスマンも国境をまたぐ移動が制限されたことで、現地の人との画面を通したコミュニケーションが増えています。都内のオフィスも大手企業を中心に事務所面積を削減、密を避けるため多拠点稼働が増えているそうです。地方や自宅近くでのテレワークも推奨されてきて船橋近郊にもテレワーク拠点が整備されつつあります。
これまで人間同士がコミュニケーションをとり、積み上げてきた信頼関係は、過去の実績をもとにAIが判断するようになってくるのかも知れません。アカウントに紐づいた情報で人の信用を判断する時代はすぐそこにきているかも知れないのです。
私たちMyFuna編集部では、その一方でそれらとは違うモノやサービスの流れが見直されるのではないかと考えています。
それは「地域や地方をベースにした経済圏」です。地域では今でも漁師さんが獲った市場出荷しない魚は、農家の規格外のダイコンやジャガイモ、キャベツなどと交換され猟師が捕まえたイノシシは、一人では食べきれない分を加工し、農家や漁師の持つそうした商品と交換されています。1100年程前の日本では、田舎に行かずとも全国どこでも当たり前に見られる社会構造でした。
現代の私たちも、カフェをオープンさせた友人がいれば、その人に会いに店を訪れます。店に集まる常連の顔を見るために店に行き、楽しく会話をして時間を過ごします。知り合いがマルシェに出店していたら、気持ちよく買い物をするでしょう。
これらの場合に、高いか安いかはそれほど問題にしないはずです。安いか高いかだけを見る消費行動も効率化しながら流れていきますが、地域社会では人と人とのつながりの中で生まれる消費も見直されていくのではないかと考えています。
株式会社myふなばし
代表取締役 山﨑健太朗

Twitter(@ MyFunabashi)
ほかにもさまざまな情報発信をしています!
★YouTube「やまけんちゃんねる」山﨑が船橋市内中心に活躍している経営者をゲストに呼んでインタビューしています
★ブログ「主婦と高齢者で地方活性化を実現する編集者・ライターという働き方」
※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください